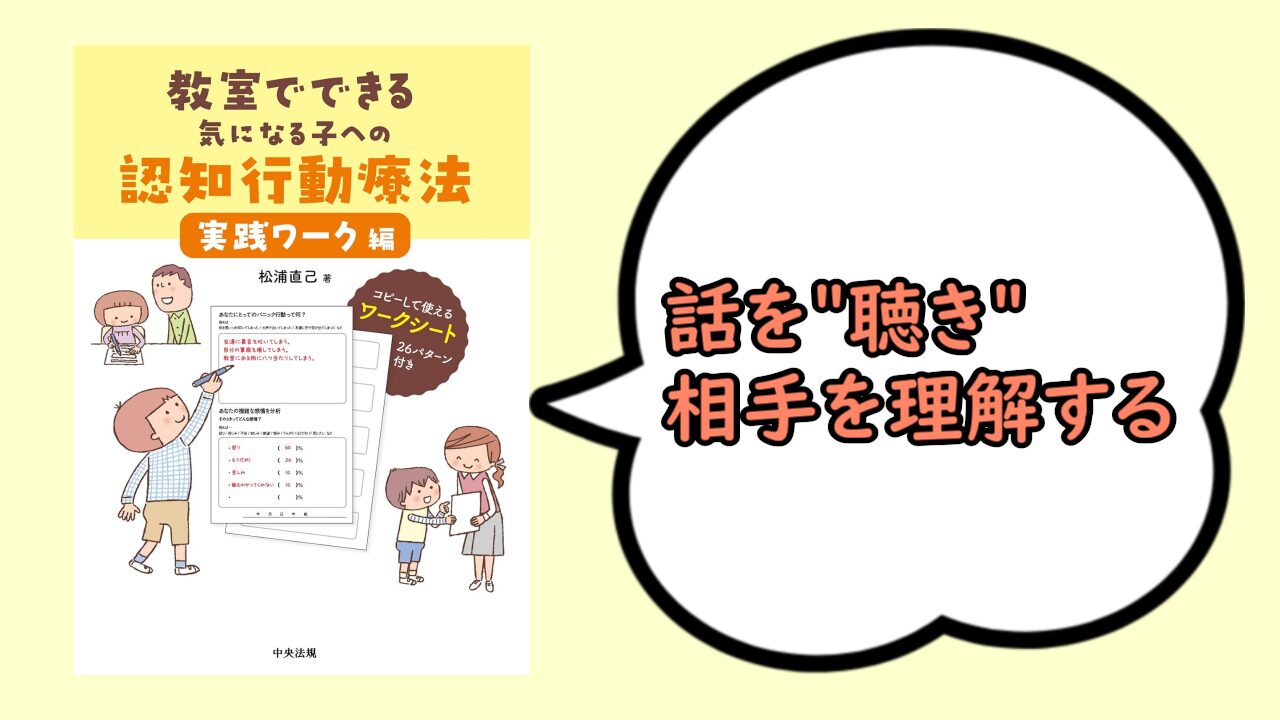概要
2020年発行
「認知行動療法」(CBT)は基本的に医療で使われる言葉で、精神療法です。
この本ではそんな認知行動療法を教育に活用し、”偏った認知を修正しながら適切な行動を増やす”ことを指します。
内容
教員の対人スキル
認知行動療法を学校で行うにあたり、必要とされる教員のスキルがあります。
まずは「共感的な事」
子どもと良い関係を作るために必要不可欠です。
子どもが楽しんでいる時には共感しやすいと思いますが
悩みや苦しみに寄り添って共感することは難しいです。
子どもに接するときに、まずは寄り添う姿勢が大切です。
そして「親しみやすい事」
子どもとの相性はあると思いますが
笑顔で対応・常に話しかける・心配な子には丁寧な対応
スキルの部分も大きいです。
緊急事態に対して子供たちが協力し合う
そんな環境ができあがっていきます。
最後に「ユーモア」
誰かがパニック行動・不適応行動を起こしていると周りはザワザワとします
そんな時にユーモアを出して雰囲気を明るくできれば効果抜群。
先生がいれば、困った時も大丈夫!
そんな安心感があればクラスのみんなも安心して生活することができます。
この本では究極の対人援助は「相手の考えを理解すること」と書かれています。
「なぜ私の言うことを分かってくれないんだろう」
↓
「私はなぜこの人のことをわかってあげられないのだろう」
と、常に「相手」を意識して接することが大切です。
しかし、相手に対して全面的な共感することはこれと似ているようで全く違います。
例を示します。
パニック行動を起こしてしまうA君
「A君はすぐパニックになって手が付けられなくなってしまうから放っておこう。友達にけがをさせてしまうかもしれないけど、それがA君だから受け入れよう」
これが全面的共感です。
この考えは意外と世の中にあふれている事象ではないでしょうか?
A君の立場に立って、どんな要因がパニック行動を起こすのか、観察・分析していこう。
この姿勢こそが「相手の考えを理解すること」に繋がります。
対大人の対応で考えてみます。
保健師さんが「Bさんの保護者が私の言うことを聞いてくれない!Bさんは発達の遅れがあって、それをアドバイスしているのに全然聞き入れない!」
この保健師さんは正しいことを言っていますが、それが良い結果を生むとは限りません。
何度も言いますが相手の考えを理解する。自分の考えを理解してもらいたいというケースは非常に多いです。
もう1つ大切な事は「意見の対立に感情を持ち込まない」ことです。
その人に対する好き嫌いの気持ちで意見を変えず、冷静になって距離感を保ちましょう。
保護者対応でもこれらの考えが非常に有効に働きます。
(教員から見て)間違ったことを保護者が言っても「違いますよ」と否定するのではなく
なぜその思考をしているのか?を考え、そこに寄り添って理解しようとする姿勢が大切です。
認知の歪みまとめ
パニックなど、困った行動が起こった時の振り返りとして活用してみてください。
本には感情や行動に働きかけるワークシートや詳しいチェックリストも付いています。
”相手を理解する”手がかりとなる思考パターンです。
全か無かの思考
ゼロイチ思考・白黒思考とも
「誰からも好かれなければいけない」
「かんぺきじゃなきゃいけない」
などを強く信じてしまうと
自分に満足することができなくなってしまい、息苦しさを感じてしまいます。
一般化のしすぎ
たった1度の嫌な出来事をずっと続くと考えてしまう思考です。
今までできなかった経験から
「うまくいくはずがない・・・」
と自信を無くしてしまったりします。
結論の飛躍
友達と少しトラブルになっただけで
「一生友達になれない」
と考えてしまいます。
勝手に悪い結果を予想してしまいます。
心のフィルター
1つのよくないことにこだわって、悪い事ばかりを思い出してしまうことです。
全体としてうまくいっていても、ちょっと気になるポイントがあったら
絶対失敗する!となって行動に映せなくなります。
マイナス化思考
友達に優しく声をかけられても「悪口を言われた」などネガティブに変換してしまいます。
もっとも厄介な認知の歪みです。
良い事なのに悪い事に勝手にすり替わってしまうのです。
拡大解釈・過小評価
客観的にみて平均以上で良い結果なのに
「自分はなにも出来ない」と感じてしまいます。
また、勝手に自分の責任だと思い込んでしまいます。
感情的決めつけ
自分の好き嫌いの感情だけで
「あいつはダメなやつだ」
と特定の嫌いな人に悪口や否定的発言をしてしまいます。
人間は感情の生き物ですが、ある程度気持ちと距離を置くスキルも必要です。
すべき思考
「みんなと仲良くしなければいけない」
「必ず全員掃除をしなければいけない」
という考えで他人と折り合いをつけることができない場合があります。
こうあってほしいという願いが強すぎて本人も苦しいです。
レッテル貼り
自分は役立たずだ
などと、こういう人間というレッテルを貼ることで、ネガティブにその人を一般化してしまうことです。
個人化
「自分のせいでチームが負けてしまった」
「あいつがいるから学校が面白くない」
個人にすべての責任があるという考え方です。
実例紹介
先ほどの
認知の歪みに加え
感情にフォーカスする
行動にフォーカスする
というアプローチで対応が紹介されています。
大まかな事例としては
かんしゃく・パニック・イライラが強い
などの困った行動に対して具体的な対策や声掛け、ワークシートでの振り返りの例が載っています。
著者
・松浦直己さん
三重大学教育学部特別支援教育特別支援分野教授
発達障碍児のための教室を経営